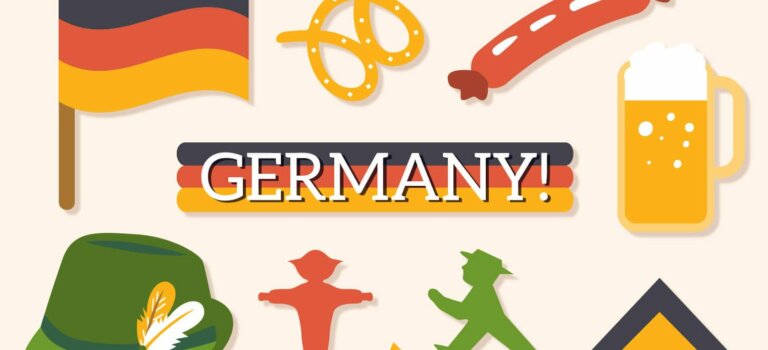今回で食べ物編は最後になります。
Kümmere dich nicht um ungelegte Eier.
直訳:まだ産まれていない卵を気にかけるな
→捕らぬ狸の皮算用
このことわざはおそらくマーティン・ルーサー
の言葉だと言われています。
似たような表現に
Man soll die Rechnung nicht ohne den Wirt machen.
直訳:主人なしに請求書を切るな
Verkaufe das Fell nicht, bevor du den Bären erlegt hast.
直訳:クマを仕留める前に毛皮を売るな
があります。
Wein auf Bier, das rat’ ich dir. Bier auf Wein, lass es sein.
直訳:ビールの後にワイン、これはお勧め。
ワインのあとにビール、これはやめといたほうが。
→同じようなものでも、うまくいくものとそうでないものがある。
このことわざはおそらく中世に由来します。
当時ビールは下層階級の飲み物で、
ワインは貴族が飲むものでした。
ワインを飲む人の仲間入りをした人、
つまり貴族は、再び下の階級に降りてはいけない、
という意味が込められているようです。
食べ物を使った表現はやはりかなり沢山ありますね。
日本とは食べるものが違うので、
日本語の表現とはかなり異なっていることがよくわかったと思います。